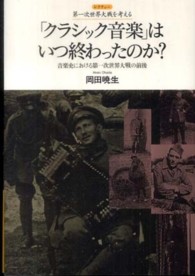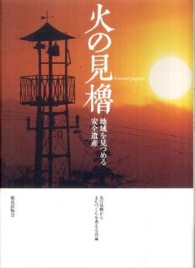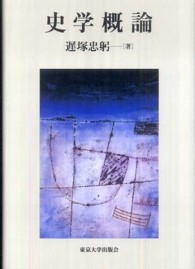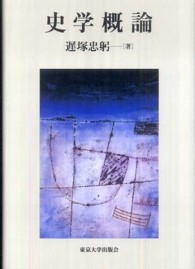
 →bookwebで購入
→bookwebで購入
歴史学とはやっかいな学問である。いくら説明しても、なかなかわかってもらえない。それは、だれもがよく知っている歴史の延長線上に、学問としての歴史 学があると勝手に思って、わかろうという気もないからである。世間一般の人びとが認識している歴史と、学問としての歴史学は、似て非なるものであることに 気づく者は、それほど多くない。そして、それをわかりやすく説明できる歴史研究者は、数少ない。そんな数少ないなかのひとりが、著者の遅塚忠躬である。
冒頭の「はしがき」で、著者はつぎのように書き出している。「歴史学に従事している人びとは、その従事する学問の性質について、大筋では共通の見解を もっているかといえば、けっしてそうではない。そこには、雲泥の差が見られ、ときには正反対の見解が対立している。したがって、私には、「公平な」史学概 論を書くことはできない」。だから、著者は、「はしがき」で「読者に対する私の学問的な自己紹介」をするという。
歴史学は、扱う時代、地域、社会、テーマなどによって、「基本的な考え方(立場)」が違う。著者の専門は、膨大な史料があり、研究蓄積が豊富な「フラン ス革命」であることを、まず念頭においてから本書を読む必要がある。そして、本書を紹介するわたしは、文献史料に乏しく、研究蓄積がほとんどない海域東南 アジア史を専門にしている。まったく「基本的な考え方(立場)」が違うはずだが、本書に書かれている多くのことに共鳴することができた。それは、学問とし ての歴史学の基本的性質を共有しているからではないだろうか。また、いまは違いを強調する時代でもないだろう。
講義に基づいて書かれた本書は、繰り返しが多い。それは、重要なことは、毎時間それを確認して講義をすすめるからである。その繰り返しでもっとも多いの が、「歴史学は何の役に立つのか」、という問いかけである。そして、それが「歴史学に関する最初にして最後の問題」であり、「社会的な意味における自己認 識」を深めるためであることを、伊藤貞夫氏のことばを借りて述べている。つまり、最初に「何の役に立つのか」を考えない歴史研究は、目標とするゴールのな い自己満足だけのための研究になるということだ。著者は、その最重要課題を、最終章「第4章 歴史認識の基本的性格」の最終節「第6節 歴史学の社会的責 任」で詳しく説明して、本書を終えている。
歴史学が学問として理解されない理由のひとつは、文学との混同や曖昧さなどから、歴史学が科学と認識されないことにある。それにたいして著者は、「歴史 学の出発点は過去ではなく現在である」ことを強調して答えようとしている。それは、尚古趣味としての歴史を学問としての歴史学と切り離すためであり、両者 を分かつものとして「考証(ある歴史的事象が事実であるかどうかを吟味する仕事)」を加え、三者を比較・検討することによって、その違いを明らかにしてい る。三者の関係を図式化すると、大中小3つの輪があり、中心は歴史学、外側が尚古趣味で、そのあいだが考証となる。三者の相違は、つぎのように表された: 「尚古趣味の場合: 価値観→過去の世界(事実性にこだわらない)」「考証の場合: 価値観→過去の事実へのこだわり→その事実の確定」「歴史学の場合: 価値観→問題関心・問題設定→確定された過去の事実を基礎とする諸事実の関連の想定・歴史像の構築」。
そして、「第3章 歴史学の境界」「第1節 歴史学とその周辺」の結論として、歴史学の営みをつぎのように定義した。「歴史学は、個人的な価値観に基づ く多様な目的をもって過去に問いかけ、その問いかけの仕方(問題設定)に適した過去の諸事実を取り扱うが、その際、さまざまな事実を確定するだけではな く、何らかの理論的枠組みに準拠してそれら諸事実間の関連を想定し、諸事実を論理的に組み立てて、その結果を仮説(ないし歴史像)として提示する営みであ る」。
著者は、「歴史学は何の役に立つのか」という疑問にたいして第1章「歴史学の目的」と第3章「歴史学の境界」で答え、もうひとつの大きな疑問である「歴 史家の言っていることはどのくらい確かなのか」にたいして第2章と第4章で答えている。その答えを理解するためには、つぎの5つの作業工程を経て歴史像が 構築されていることを確認する必要がある。「�問題関心を抱いて過去に問いかけ、問題を設定する」「�その問題設定に適した事実を発見するために、雑多な 史料群のなかからその問題に関係する諸種の史料を選び出す」「�諸種の史料の記述の検討(史料批判・照合・解釈)によって、史料の背後にある事実を認識 (確認・復元・推測)する。(この工程は考証ないし実証と呼ばれる)」「�考証によって認識された諸事実を素材として、さまざまな事実の間の関連(因果関 係なり相互連関なり)を想定し、諸事実の意味(歴史的意義)を解釈する」「�その想定と解釈の結果として、最初の問題設定についての仮説(命題)を提示 し、その仮説に基づいて歴史像を構築したり修正したりする」。
まず、著者は「第2章 歴史学の対象とその認識」で、「歴史的世界を構成しているさまざまな事実を認識する作業(事実の確認や復元)」を検討し、「歴史 をよくできたお話なのだ」という物語り論をしりぞけた後、第4章で「認識された個々の事実を素材として、それら諸事実の間の諸関連を想定し、事実関係を解 釈して、みずからの歴史像構築のための命題を提示する作業」を検討している。別のことばで言えば、前者の事実認識に関する見解を前提にして、後者の歴史認 識の基本的性格を第4章で検討している、ということになる。
これら2つの大きな疑問への答えは、第4章第6節へと収斂していく。この節は、「終章」あるいは「結語」ともいうべきものである。その冒頭で、著者はつ ぎのように述べている。「歴史学の目的と効用が、したがってまた歴史家の職分が、みずから思索を重ねることを通じて読者を思索に誘うことにある、と述べ た。そのことについて、私は聊かの疑念も持っていない。しかしながら、そのことは、必ずしも、歴史家は、研究室で思索を凝らしてその結果を教室でまた著作 で学生や読者に伝えるだけでよい、ということにはならない。歴史学の研究という営みは、その他の研究活動と同じく、われわれの文化的な営為の一環であっ て、経済学や法学が政策提言を目指すのとは異なっていようとも、その営為の遂行について社会的な責任を負うべきであろう」。
最後の短い「むすび」の最後で、著者は「歴史学に限らず、おそらくは科学一般が、いま、パラダイムの転換を迫られているのではなかろうか」と述べ、「歴 史学の新たな飛翔を若き世代に期待しつつ、本書をここで閉じることにしよう」と結んでいる。本書によって、確認させられたことの多くは、西欧を中心に発展 した近代歴史学の成果である。それはそれで、歴史学の基本を学ぶために重要である。しかし、近代歴史学が扱った地域や社会、人びとがひじょうに限られてい たことを考えると、グローバル化がすすみ複雑化する社会を念頭におかなければならないこれからの歴史学を考えるとき、フランス革命を専門とした歴史研究者 が語る「史学概論」には限界がある。どこの大学でも「史学概論」を講義するのは、西洋近現代史を専門とする年配の研究者がふさわしい、と考えていること自 体が、今日の歴史学の問題と言わなければならないだろう。本来、世界史学を専門とする者がふさわしいのだろうが、時代、地域、社会やテーマなどのよって、 史料、研究者数、研究蓄積の多寡に大きなばらつきがある現在の状況では、とても世界史学にもとづいた「公平な」史学概論など講義できるわけがない。まずは 本書を土台に、個々の歴史研究者が、現実の社会と向き合いながら、「社会的責任」を意識し、営為を遂行していくしかないだろう。
そして、最後に確認しておきたいのは、本書の帯の裏に書かれている著者の意図がわからない者は、尚古趣味の歴史とはまったく時限の違う学問としての歴史 学があることを少なくとも知ってほしい。「歴史学は、すでにできあがった知の体系ではなく、躍動し変貌し続ける生き物である。それは、新たな領域を開拓 し、従来とは違った観点から対象を見なおし、また、新たな方法を編み出したり隣接諸科学から借用したりしながら、日々その相貌を変えつつある。しかし、そ れが一つの学問であり続けるからには、そこには変わらざる基本的骨格があるだろう。私は、この書物で、歴史学の骨格をなす基本的性質を検討しようとしてい る」。
生き物である歴史学とつきあうには、日々躍動し変貌しつづける社会から目が離せない。歴史学とはまことにやっかいな学問であり、それだけに魅力があり、社会的責任をともなう。
 →bookwebで購入
→bookwebで購入